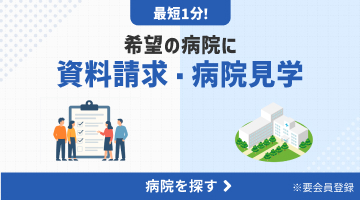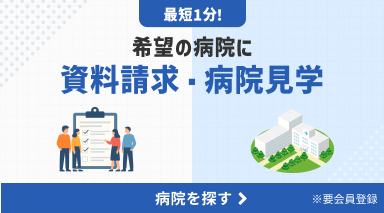臨床推論で注意すべき6つのバイアス 明日から役立つ臨床推論!vol.2【総合内科・徳田安春先生】
前回(臨床推論が不十分だと、どうなる?!-訴訟からひもとく重要性) でも述べたとおり、直感的な判断を下すシステム1の最大の欠点は、“自分のバイアスが診断に影響を与える恐れがある”ということです。しかし、どんな種類のバイアスが存在し、自分がそのバイアスにとらわれていないかを意識することによって、バイアスに陥るリスクは減少させられると言われています。今回は、臨床推論の過程で注意しなければならない代表的なバイアスをご紹介します。
1.
Anchoring Bias
最初に考えた診断に固執して考えを改めない。これはありがちなバイアスですね。
2.
Availability Bias
最近遭遇した類似症例と同じ疾患を考えてしまう。インフルエンザシーズンは、熱で来た患者さんが皆インフルエンザに見えてしまうなどが挙げられます。
3.
Confirmation Bias
自分の仮説に適合したデータは受け入れるけれど、不適合なデータを無視してしまうというバイアスです。
4.
Hassle Bias
自分が最も楽に処理できるような仮説のみを考える。早く家に帰りたい時に患者さんを診ると、何だか軽症に見えてしまう。金曜日の夕方などは特に要チェックですね。
5.
Overconfidence Bias
前医や指導医の意見に盲目的に従ってしまうというバイアスです。指導医や前医も、間違えることはあります。「後医は名医」という言葉にもある通り、後医の方がたくさん情報を得られる立場な分、前医よりも正しい情報を判断できる環境にあるのですから、前医の判断に対して客観的にダブルチェックしようという姿勢は忘れずに持っておきましょう。
6.
Rule Bias
通常は正しいルールであっても、過信するとそれにミスリードされてしまうというバイアスです。数々の経験則に裏打ちされているクリニカルパールが、どんな時にでも100%正解であるわけではありません。クリニカルパールを活用するときも、「例外がある」ことを常に意識しておきましょう。
Question
―バイアスの存在を知っていても、実際にバイアスにとらわれないように日常診療をこなせるか分かりません。徳田先生ご自身は実臨床で何か意識されていることはありますか?
自分の診断が正しかったかどうか、週1回程度、レビューすることをお勧めします。仮に何らかのエラーが起こった場合は、その時自分が何らかのバイアスに引っ掛かっていなかったかを検証する。こうしたレビューを繰り返すことで、徐々にバイアスにとらわれずに診断が下せるようになると思います。